パラダイムシフトとは?
「7つの習慣」第2弾。
本日はパラダイムシフトについて説明をします。
「パラダイムシフトってなに?」と言葉だけ聴くと馴染みのない単語ですよね。
「パラダイム」とは『その時代の規範となるような思想や価値観』を表し、「シフト」とは『移行・切替・変化』を表す言葉です。
つまりパラダイムシフトとはこの2つの言葉を合わせた
『思想や価値観の変化』を説明した言葉になります。
一般的なパラダイムシフトの事例
一般的なパラダイムシフトを説明すると以下のような例があります。
ガラケーからスマホへの変化
物を所有することから共有(サブスク)への変化
会社勤務から在宅勤務への変化
これを見て皆さんどう思いましたか。
「パラダイムシフトの変化は理解できた。でもこんな世の中を変えるような事は出来ないから自分には関係ないな」と思った方が大半かと思います。
ここで説明したパラダイムシフトはあくまで一般的な事例になります。
僕が本当に伝えたいことは、僕達は仕事や生活でもパラダイムシフトは簡単に起こせるという事です。
「えっ!!そんな事を出来るの?」と思った方。
どうすればパラダイムシフトができるのか?
以下にその説明を書きます。
どうすれば私達はパラダイムシフト出来るのか?
パラダイムシフトをするための1番大切なことは物の見方を変える事です。
パラダイムシフトの始まりは「SEE(見る)」ことから始まります。
正直これが出来れば、難しいテーマでなければ簡単にパラダイムシフト出来てしまいます。
でも、なぜ多くの人は「見る事が出来ないのか?」
一言で片付けるのは難しいですか、あえて一言で言うなら「見ない方が楽だからです。」
これは心理学用語で『現状維持バイアス』と言います。
未知のものや変化を受け入れず、現状維持を望む心理作用です。
現状維持しているその瞬間は、ある種の安心感があるかと思います。
しかし現状維持というのは喜んではいけないのです。
なぜかというと「世の中は少しずつですが変化・進化」をしています。
そんな中、ひとり現状維持をしていれば自然と周りと差がついてしますのは当然の結果です。
一度開いた遅れを取り戻すのは大きな労力が必要です。
では次に僕が実際に仕事で起こしたパラダイムシフトを説明します。
先に言いますが、小さなパラダイムシフトです。
僕が実現した小さなパラダイムシフト
これは以下リンク先の7つの習慣の前提である『インサイドアウト』の際に説明した時と同じ実体験で説明をしていきます。
まだ『インサイドアウト』の記事について読んでいない方はリンク先より読んでみてください。

僕が現在、会社に所属しているIT組織はコールセンターのような役割ではありませんが、
ユーザ部門からの問合せが1日に10件以上来ることを当たり前と思っている部門でした。
長く組織にいる人は毎日矢のごとく降り注ぐ、ユーザ部門からの問い合わせを
必死に調べて回答していました。
しかし当時僕は配属されたばかりということもあり、その現状を素直に受け入れられませんでした。
はっきり言って頑張っていることに「違和感」を感じたのです。
そこで私はまず「SEE(見る)」ことから始めました。
ここでいう見るとは問合せ台帳を作成して一元管理すること。
実際にどんな問合せを受けて、いつ、誰が、どのような回答をしているかまで整理しました。
昔からいる人からすると何をしているのだろうと疑問を感じたかもしれません。
そうすると人によって回答の品質にばらつきがあることや、類似問合せも散見されました。
この「見えた」ものを分析して、それを同じ組織メンバーに共有しました。
これが「SEE(見る)」ことの次に当たる「DO(実行)」です。
「DO」をすると必ず、他者からの反応が返ってきます。
最初は批判的な反応でした。
しかし実際に分析した問合せ台帳の中身を共有すると、自分たちの落ち度も分かるようになります。
その落ち度に対して一つずつ対処していきます。
そうすると「GET(結果を得る)」ことに繋がっていきます。
現在の1日の問合せの数は0件〜2件までと(50%〜100%削減)まで繋がりました。
パラダイムシフトを実現しての感想
大きなパラダイムシフトをすることは確かに難しいですが、このように小さなパラダイムシフトは簡単に出来ます。
会社に限らず、家庭・コミュニティー・友人など多くの場面でパラダイムシフトは可能です。
まずは小さな違和感を感じたら「SEE(見る)」ことから始めてください。
パラダイムシフトをすると自分の世界・環境も大きく変わります。
その風景は非常に「楽しい世界」です。
それでは本日はこのへんで。
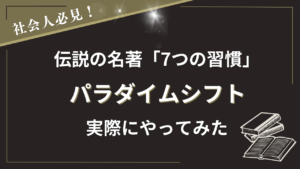

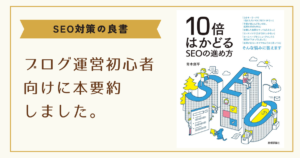

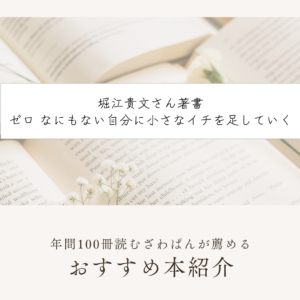
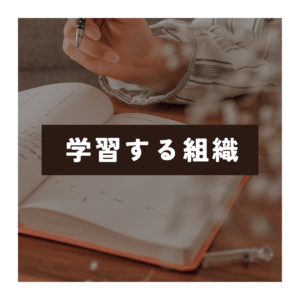



コメント