 ざわぱん
ざわぱんビジネス書ブログを運営しています。
ざわぱんです。
今回はピータ・M・センゲさんの著書「学習する組織」について説明します。
いつも通り結論から。
この本は組織の学習能力に影響を与える「3つの柱」及び、「5つの重要な学習領域」について教えてくれる本です。
従来の組織は経営者や、マネージャが組織を管理するスタイルでした。
一方「学習する組織」は組織内の人々が自ら考えて意見し合いながら成長するスタイルです。
例えば組織の中でもこのような人たちいませんか?
・教育の機会がなく成長ができない
・上司から指示を受けていないので、自分からアクションをしない など
自ら進んで学習をしない組織は必然的に弱くなっていきます。
ではどうすれば「学習する組織」を築けるのか。
それについて説明します。
第1章 学習する組織の3本の柱
学習する組織は3本の柱で支えられています。
それぞれについて説明します。
①志の育成
②複雑性の理解
③共創的な会話の展開
志の育成について
志の育成は、「自己啓発」や「目標達成」のために内面的な意欲や情熱を育てるプロセスを指します。
志を持つことは、人生の目的や方向性を明確にし、困難に立ち向かう力を養うのに役立ちます。
以下に、志の育成に役立ついくつかのアプローチを紹介します。
1)目標設定
自分の望む将来のビジョンを明確にし、そのための具体的な目標を設定します。長期的目標から短期的目標ものまでさまざまですが、目標を持つことで志を高めることができます。
2)自己認識
自分自身をよく理解し、自分の価値観や強み、弱みを把握します。自己認識を深めることで、自己意識が高まり、志を持つ力が強化されます。
3)持続的な学習
新しいスキルや知識を習得し続けることは、志を高めるのに役立ちます。自己啓発を通じて、成長し続ける姿勢を持つことが大切です。
複雑性の理解
複雑性の理解とは正に言葉の通り「複雑なことを理解できる」ことです。
志を立てても、その問題解決の方法を正しく把握できなければ実現できません。
以下に、複雑性の理解に役立ついくつかのアプローチを紹介します。
1)単純化する
複雑だから難しいのです。ならばそれを単純化して見ることです。
2)全体像を把握する
複雑な物事も俯瞰してみることでその複雑性がなぜ出来出ているのか見ることが出来ます。僕個人としては複雑性を理解するときは「単純化」と「全体像把握」をよくします。
共創的な会話の展開
共創的な会話とは、異なる立場の人が協力して物事を創り出すための会話を意味します。
共創的な会話とは、異なる意見や視点を持つ人々が協力して新しいアイデアや解決策を生み出すために行われる会話です。イノベーション、問題解決、意思決定、アイデアの発展など、さまざまな分野で活用されます。
以下は、共創な会話の要点です。
1)活発なディスカッション
意見の対立や異なる視点からのディスカッションは、新しいアイデアの創造に役立ちます。ただし、建設的な議論を心掛けましょう。
2)多様性を尊重する
共創的な対話では、異なるバックグラウンド、専門知識、経験を持つ人々が参加します。多様な視点を受け入れ、尊重することが重要です。
3)アクティブリスニング
注意深く相手の発言を聞き、理解することが求められます。質問を通じてさらに深い理解を得ることも大切です。
4)アイデアの共有と統合
自分のアイデアを率直に共有し、他のアイデアと統合する方法を模索します。新しいアイデアや解決策を共同で構築しましょう。
学習する組織の実現には、3本の柱のバランスが重要です。
3つの能力をバランスよく伸ばし、学習する組織の実現を目指しましょう。
第2章 学習する組織に必要な5つのディシプリン(学習領域)
学習する組織には、それぞれの柱ごとに学習領域があります。
3本の柱を伸ばすためのディシプリンは、下記の5つです。
具体的に解説します。
①志の育成
1)自己マスタリー
2)共有ビジョン
②複雑性の理解
3)システム思考
③共創的な会話の展開
4)メンタルモデル
5)チーム学習
自己マスタリー
自己マスタリーとは、思い描くビジョンと現実のギャップを埋めるための継続的学習を意味します。
学習する組織のベースであり、組織が成長し変わるために欠かせない部分です。
自己マスタリーのポイントは、次の通りです。
・自分が何者で、何のために存在していて、どんな貢献をしたいかなどを言語化できている状態
・自分が心から求めている結果を生み出すために、自身の能力と意識を絶えず伸ばし続けること
・自分にとって何が大事かをつねに明らかにしつづける活動をしている
・自分自身を変革すること
共有ビジョン
自己マスタリーは個人が持つビジョンがベースとなります。
一方、共有ビジョンは組織全体が共有するビジョンです。
共有ビジョンのポイントは、次の通りです。
・組織全体で共有する使命、ビジョン、価値観
・地域全体で共有する「ぶれない芯」となるビジョン
・個人のビジョンを重ね合わせて抽象化したもの
・組織のメンバーが共有して抱く未来への憧憬
システム思考
システム思考とは、物事の全体像を捉え、さまざまな要素とのつながりを把握したうえで、最も効果的な解決法へ向かうアプローチのことです。
システム思考は、お互いに影響しあう要素や構造を一つの「システム」として捉え、それぞれの要素が与える影響や作用を一つの「図」に落とし込むことで、全体像を把握して、課題解決や施策を検討するための手法です。
システム思考で目指すべきポイントは、次の通りです。
・物事を点ではなく線で考える
・相互作用に注目する
・物事を全体的に見る
・本質的な問題や課題に着手する
システム思考は、複雑性の理解に大きく影響します。
メンタルモデル
メンタルモデルとは、認知心理学で用いられる用語で、物事の見方や行動に大きく影響を与える「固定観念」や「暗黙の前提」のことを指します。個人の思い込みや間違った認識である場合、組織改革のためには変化と改善が必要です。メンタルモデルで意識すべきポイントは、次の通りです。
・自身の言動や考え方を振り返る
・思い込みや間違った認識を改善する
・メンタルモデルを共有し自覚する
チーム学習
チーム学習とは、グループで一緒に探求、考察、内省を行うことで自分たちの意識と能力を共同で高める方法です。
チーム学習で目指すべきポイントは、次の通りです。
・組織に関わる人々と対話する
・意見交換やディスカッションで学習を深める
第3章 まとめ
今回はピータ・M・センゲさんの著書「学習する組織」について説明しました。
この本の結論は以下の通りです。
学習する組織は以下3本の柱で支えらています。
①志の育成
②複雑性の理解
③共創的な会話の展開
そしてその以下5つのディシプリン(学習領域)で成立しています。
①志の育成
1)自己マスタリー
2)共有ビジョン
②複雑性の理解
3)システム思考
③共創的な会話の展開
4)メンタルモデル
5)チーム学習
皆様の組織は「学習する組織」になっているでしょうか。もし「学習する意識が見えない」「指示待ち状態になっている」のであれば、この中の1つでも実践してみるとよいです。
難しく考える必要はありません。
まずは行動してみる。
たったそれだけです。
それでは本日はこのへんで。

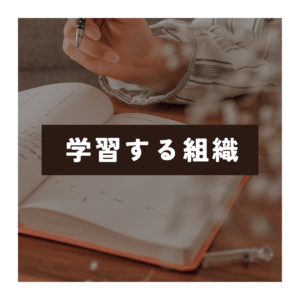

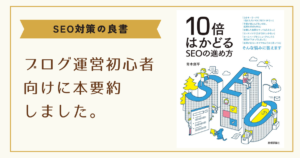

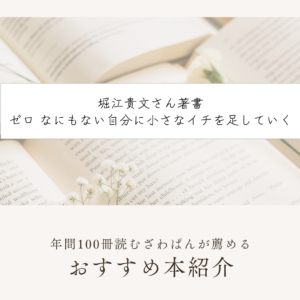




コメント